輸入果物の防カビ剤・防ばい剤の危険性とは?おもな種類(OPP・TBZ・イマザリル)と落とし方
※記事内に広告を含む場合があります
当サイトは更新を終了しました。
長きにわたり当サイトを愛読、応援くださった方々には誠に感謝しております。
※この記事の内容は執筆時点のものです。サービス内容・料金など、現時点の最新情報とは異なる場合がございます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

防カビ剤、防ばい剤は、食品に付着したカビの繁殖を防止するのに用いられる食品添加物です。
長期的な運搬や貯蔵が必要な輸入果物(オレンジやレモン、グレープフルーツ、バナナなど)が使用の対象になります。
この記事の目次
輸入果物に防カビ剤を使用する理由

外国産のかんきつ類やバナナは、船便で長時間かけて運ばれるので、私たちがスーパーの店頭で手に取るまでには、収穫からかなりの時間がたっています。
生の果物を長期的に輸送したり貯蔵したりすると、カビが生える可能性が高くなります。
食品の表面に防カビ剤を使用することで、食品の品質を保つ効果があります。
カビた食品は食べられないことを考えると、防カビ剤の使用は、私たちが安心して食べるためには必要不可欠な処置と言えます。
◆防カビ剤、防ばい剤は同じ意味
防カビ剤、防ばい剤は、いずれも「防黴剤」と書きます。
黴は音読みで「バイ」、訓読みで「かび」で、防カビ剤、防ばい剤は同じものです。
防カビ剤は「食品添加物」扱いで表示義務がある

食品添加物とは「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」と食品衛生法で定義されています。
残留農薬は「農薬を使用した結果、消失せずに農作物に残った農薬」のことで、収穫後の食品に使用される防カビ剤は食品添加物扱いになります。
防カビ剤として使用される物質のなかには、農薬(殺菌剤)として用いられるものもありますが「どのタイミングで使ったのか?」によって、農薬か食品添加物かに分かれます。
ちなみに「ポストハーベスト農薬」は、収穫後の農産物に使用される殺菌剤や防カビ剤のことで、食品添加物の言い方を変えたものです。
防カビ剤が使用された食品を販売する際は、パッケージ売り、バラ売り問わず、陳列棚、品名札、値札などに「防カビ剤(物質名)使用」の表示をする必要があります。
そのため、同じような輸入果物でも「防カビ剤や物質名」の表示がなければ、使用はされていません。

あわせて読みたい:
実は輸入農産物は危険がいっぱい?ポストハーベスト農薬の問題とは
防カビ剤・防ばい剤の種類と特徴
輸入果物に防カビ剤として使用される物質は1つではなく、複数を併用することが多いです。
健康に影響を与えないように、食品衛生法によって使用可能な食品や最大残存量などの使用基準が定められています。
OPP(オルトフェニルフェノール)
対象果物:かんきつ類
防カビ作用が高く、かんきつ類の表皮に散布、塗布して用いられます。
チアベンダゾールやピリメタニルなどのほかの防カビ剤と併用されることも多いです。
日本ではもともと農薬(殺菌剤)として1955年に登録、1969年に失効しており、現在はかんきつ類の防カビ剤(食品添加物)目的のみに使用されています。
OPPの食品添加物としての認可には、1970年代にOPPを使用したかんきつ類の輸入を巡り「アメリカの強い要求に日本の厚生労働省が応じた」という経緯があります。
TBZ(チアベンダゾール)
対象果物:かんきつ類、バナナ
TBZ(チアベンダゾール)は、食品添加物(防カビ剤)のほかに農薬(殺菌剤、殺線虫剤)や動物用医療品としても利用されている物質です。
かんきつ類にはワックスにTBZを混入して収穫後の果物に浸透させたり、バナナには収穫時にスプレーやチアベンダゾール溶液に浸すことで、防カビを行ないます。
イマザリル
対象果物:かんきつ類(みかんを除く)、バナナ
イマザリルは、ベルギーの製薬会社ヤンセン社の商品名で、物質名としては「エニルコナゾール」です。
海外では農薬(殺菌剤)として使用されることもありますが、日本では農薬としての登録はなく、防カビ剤(食品添加物)のみで取り扱われています。
カビの発生を防止する効果が高く、比較的水に溶けやすい性質があります。
使用する際は、ワックス処理液と一緒に浸けたり、スプレーしたりして、果物の表面に防カビ処理を施します。
フルジオキソニル
対象果物:キウイ、かんきつ類(みかんを除く)、アンズ、黄桃、ザクロ、すもも、西洋ナシ、ネクタリン、びわ、マルメロ、モモ、リンゴ
フルジオキソニルは、1984年にスイスのチバガイギー社(現:シンジェンタ社)が開発したフェニルピロール系の殺菌剤です。
カビ胞子の発芽や菌糸の生育を阻害する作用があることから、殺菌剤(農薬)以外に防カビ剤(食品添加物)としても用いられています。
以前はかんきつ類の使用に限定されていましたが、2011年からはキウイやモモなどの幅広い輸入果物に使用が認可されています。
ピリメタニル
対象果物:アンズ、黄桃、かんきつ類(みかんを除く)、すもも、モモ、西洋ナシ、マルメロ、リンゴ
ピリメタニルは、2013年に使用が認められた比較的新しいタイプの防カビ剤です。
食品に使用することで、糸状菌の生合成を阻害したり、死滅させたりする効果があります。
日本では1999年に殺菌剤として農薬登録後、2005年に失効しており、現在は農薬としては使用されていません。
防カビ剤、ポストハーベスト農薬の落とし方
防カビ剤(ポストハーベスト農薬)は「果実の皮」部分に付着しています。
そのため、果物の表面をよく水洗いして、皮をむいて食べれば、防カビ剤を多量に摂取する心配はありません。
果物を切るときも、果肉部分から切るようにすれば、防カビ剤が果肉部分に付着しません。
「皮ごと使う、食べる」という場合は、以下のような方法を用いれば、さらに念入りに防カビ剤を落とせるので、安心感があります。
塩でこすり洗いをする

手のひらに小さじ1~2杯の塩を入れて、果物を塩で揉むように表面をこすり洗いすることで、表面に付いたワックスや防カビ剤が落ちやすくなります。
最後に水でよく洗えば、塩に付着したワックスや防カビ剤も一緒に流せます。
野菜・果物に使える洗剤を使用する

用途に「野菜・果物」の表示のある食器用洗剤や、野菜洗い用洗剤で、果物の表面を洗います。
洗剤には雑菌を落とす作用もあるので、除菌効果も期待できます。
スポンジやタワシに洗剤を付けて、食器を洗う感覚で果物の表面をこすり、水でよくすすぎます。
重曹水に浸けて洗い流す

ボウルに小さじ1~2杯の重曹(炭酸水素ナトリウム)を入れて、よく混ぜて溶かして重曹水を作ります。
果物を重曹水に約30秒~1分浸けたあと、水で洗い流します。重曹以外にも塩や酢を使う場合も同様の効果があります。
下ゆでをする(ゆでこぼす)

マーマレードやオレンジピールなど、果物の皮を食べるときにも使われる方法です。
鍋にお湯を沸かして、果物を入れて、30秒ほど浸けたあと、流水で果物をよく洗います。
防カビ剤の危険性:問題が指摘されており、避けた方が安心
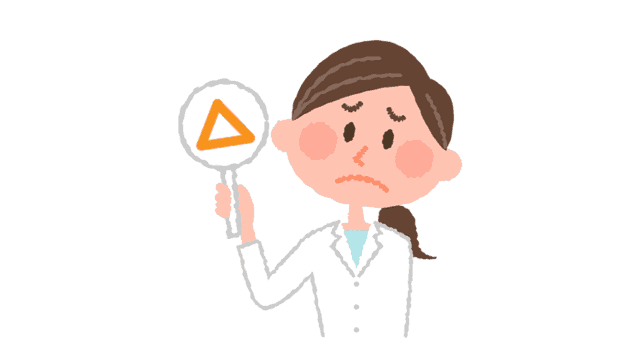
果物の収穫後に、安全性を高めるために使用される防カビ剤(ポストハーベスト農薬)には、発がん性や催奇形性(胎児に奇形が起こる危険性)物質が含まれているという指摘もされています。
◆発がん性、発がん性の疑いがある物質
OPP(オルトフェニルフェノール)、OPP-Na(オルトフェニルフェノールナトリウム)
◆急性毒性が強く、臓器に影響を可能性がある物質
イマザリル、ジフェニル
◆催奇形性、催奇形性の疑いがある物質
TBZ(チアベンダゾール)
ただし防カビ剤には使用基準が定められており、健康に影響が出るほどの量を摂取する心配はありません。
また日本に外国産の農産物が輸入される際、厚生労働省の検疫所で検査を受けており、規定値を超えたものは、輸入禁止の措置が取られます。
防カビ剤は一切使用しないと、カビが発生したり、腐ったりすることを考えると、輸入果物を安心・安全に食べる為には必要不可欠なものです。
とはいえ不安は残るので、輸入果物を買ったり、食べたりするときは以下のことを心がけるとよいと思います。
- 「防カビ剤/防ばい剤」の表示がない果物を購入する。
- 食べる前に果物の表面をよく洗ったり、皮を厚く剥いたりする。
また皮ごと料理やお菓子作りに使いたいときは、防カビ剤が不使用の国産果物を選ぶなど、基準を設けることをおすすめします。

 関連記事
関連記事








