台湾の万能調理器「大同電鍋」とは?サイズの選び方からおすすめレシピまで徹底紹介
※記事内に広告を含む場合があります
当サイトは更新を終了しました。
長きにわたり当サイトを愛読、応援くださった方々には誠に感謝しております。
※この記事の内容は執筆時点のものです。サービス内容・料金など、現時点の最新情報とは異なる場合がございます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

電鍋(ディエングォ)は、台湾の家庭で使われている電気釜です。
おもに「炊く」「煮る」「蒸す」「温める」の調理法に使えます。
数ある電鍋のなかでもっとも有名で愛用されているのが「大同電鍋(ダートンディエングォ)」です。
1960年に日本の東芝と台湾の大同公司の技術提携により誕生後、ロングセラーを続けています。
以前は台湾の現地に行かないと購入が難しかったのですが、Yahoo!ショッピングで日本公式販売店がオープンしたことで、非常に買いやすくなりました。
この記事の目次
大同電鍋の特徴と使い方
大同電鍋の使い方は非常に簡単です。
基本的に内釜に材料を入れて、外釜に水を入れて、外フタを閉めて、スイッチを入れて、あとはできあがるまで待つだけです。
スイッチを入れると、加熱が開始されます。加熱後、しばらくすると外釜の水が蒸発し始めます。水がなくなると、温度が急激に上昇します。
その後、一定の温度に達すると温度検出スイッチが作動して、自動的に保温状態に切り替わる…という仕組みになっています。
簡単に言えば「食材と水を入れて、スイッチを入れたあとは、調理を任せっぱなしにする」のが、大同電鍋の使い方です。
外釜に入れる水の量によって加熱時間が異なり、タイマーも温度調整機能もありません。
そのため、最初はどう使えばよいか戸惑うと思いますが、使っていくうちに何となくコツが掴めてきます。
豆知識:大同電鍋は「大同公司の電気釜」の意味
電鍋(ディエングォ)は、大同以外にもさまざまな家電メーカーが製造をしています。
大同電鍋は、大同が「メーカー名」、電鍋が「電気釜(電気製品名)」にあたります。
たとえば「タイガー魔法瓶」や「日清カップヌードル」をイメージするとわかりやすいかと思います。
ちなみに日本で主流の(電気)炊飯器は、台湾では「(電腦)電子鍋」と呼ばれています。
各パーツの名称と利用方法

電鍋にはほかの調理家電では見ないようなパーツや付属品もあります。
各パーツの名称と使い方を簡単に説明します。※()は台湾での名称です。
◆外フタ(鍋蓋)
調理時に使うフタです。調理中は熱くなるので、ツマミ以外の部分を素手で触るとヤケドの危険性があります。
◆外釜(外鍋)
大同電鍋の本体を指します。
外釜でも調理(焼く、炒める、煮込む)は可能ですが、大きくて洗うのが大変なので、内釜で済むような料理であれば、内釜を使った方が楽です。
外側(外殻)の部分は、調理中に熱くなりやすく、また水洗いできないので注意してください。
外釜の持ち手の片方に金属製のフックが付いていますが、これは外フタを引っ掛ける用です。
◆内釜(内鍋)
「炊く」「煮込む」のときに使います。
直火やIHでの使用もOKらしいのですが、私はまだ使ったことがないです…。
◆内フタ(内鍋蓋)
内釜にぴったり合う内釜フタは調理中には使いません。内釜で食材を保存したり、フタをしたいときに利用したりします。
◆スチームプレート(蒸盤)
「蒸す」調理で使います。
スチームプレートは凹凸どちらでも使用可能ですが、凸で使った方が、食材が水に浸からずに済みます。
凹で使いたいときは、脚付き網が必要になります。
◆アース線(接地線)
アース線は使わなくても電鍋は使用可能です。
感電などの防止のためにもアース端子付きコンセントを使うときは、アース線を取り付けた方が安全です。
◆計量カップ(軽量杯)
1杯あたりの分量は日本の米計量カップと同じです。
「1カップ=180cc」で、一般的な計量カップよりも20cc少なくなっています。
◆電源線
本体とコンセントを繋ぎます。
取り外し可能で、本体に取り付け時は、斜め上に押し込むようにすると入りやすいです。
◆しゃもじ(飯匙)
ご飯をよそう際に使います。
得意なレシピ

大同電鍋は外釜に水を入れて加熱する「蒸し炊き方式」の調理家電です。
おもに「炊く」「蒸す」「煮込む」が得意で、大同電鍋のレシピ本を見ても「内釜に材料を入れて、外釜に水を入れて、フタをして加熱する」系の料理法が大半を占めています。
調理中はカタカタ音がして、隙間から蒸気が勢いよく出ることがありますが、吹きこぼれる心配はありません。
ちなみに外釜に水を入れず、外釜や内釜を使って炒め物や焼き物もできます。
ただし油を多めに入れないと、食材がくっつきやすく、後片付けが大変なので、フライパンやフッ素加工の鍋で行なった方が便利です。
炊く(炊飯)
ご飯やおかゆ、炊き込みご飯を作るときは「米計量カップ」と「内釜の目盛り」を使います。
基本的な使い方は炊飯器と同じです。2~3合分のお米であれば、蒸らしの時間込みで、約25分~40分で炊き上がります。
ご飯
◆材料(3合分)
米:3杯
内釜の水:米が入った状態で3目盛り(3刻)
外釜の水:0.5~1杯
◆作り方
1.内釜に洗った米と分量の水を入れます。
2.外釜に分量の水を注ぎます。
3.内釜を外釜に入れて、外釜をしめます。
4.スイッチを下げます。
5.スイッチが上がったあとは、保温状態で約10~15分蒸らします。
おかゆの柔らかさ調整は、内釜に入れる水の量やフタを開けた状態での保温時間で調節します。
おかゆ
◆材料(1~2人分)
米:1/2杯
内釜の水:3杯+1/2杯
外釜の水:2杯
◆作り方
1.内釜に洗った米と水を入れます。
2.外釜に水を注ぎます。
3.内釜を外釜に入れて、外釜をしめます。
4.スイッチを下げます。
5.スイッチが上がったあとは、保温状態で約15分蒸らします。
蒸す

外釜+スチームプレートの組み合わせで、さつまいも、トウモロコシ、茶碗蒸し、プリン、肉まん、蒸しパンなどの「蒸し物」もできます。
電鍋の外釜の直径に合うセイロを購入すれば「せいろ蒸し」も可能です。
ほかにも冷ご飯やおかずなどの温め直しにも使えます。
◆使い方
1.外釜に水を入れる。
入れる水の量は、計量カップ半分~2杯分が目安です。
2.スチームプレートと蒸す食材を置く。
平皿に入れるとスチームプレートや外釜の内側が汚れずに済み、後片付けが楽できます。
3.外釜のフタを閉めて、スイッチを下げる。
煮込む

スープや煮物などの煮込み料理には「内釜」を使います。
外釜に直接材料を入れて作る方法もありますが、正直「電鍋本体を洗うのが重くて面倒」なので、内釜で事足りるのであれば、内釜を使うことをおすすめします。
◆使い方
1.内釜にスープや煮物の材料を入れる。
2.外釜に水を入れて、外釜のフタを閉めて、スイッチを下げる。
電鍋専用のレシピではなくても、いつも鍋やフライパンで作っている料理のレシピをそのまま使えばOKです。
外釜に入れる水の量は「1杯分」が目安で、あとは保温での余熱調理で何とかなります。
私がおでんやお節用の煮染め、黒豆を大同電鍋で作ったときも、一般的な料理のレシピを使いましたが、問題なく美味しくできました。
作る前に味を決めてしまえば、あとはスイッチを下げるだけでよいのは、かなり助かります。
ただしずっとフタをしたまま調理をする関係で煮汁はまったく減らないので、煮物などは材料が浸かるくらいの分量で作った方がムダがありません。
煮詰める料理には不向き

基本的に調理中にフタを外すことがないので、水分がまったく蒸発しません。
外釜の水がなくなったあと、外フタを開けて保温状態にしていても、出ていく水分量はたかが知れています。
そのため、たとえば照り煮や照り焼きなど、調理中にフタを開けて水分を飛ばしながら食材と煮汁を煮絡めるようなレシピには不向きです。
購入場所は日本と台湾どちらがよい?

大同電鍋の入手方法は、以前は「台湾の現地で買って帰る」が主流でした。
2015年春に大同公司が日本進出を果たし、Yahoo!ショッピングに日本公式販売店がオープンしたことで、日本にいながら大同電鍋が購入できます。
日本で購入する場合は、現地よりも高いのですが、日本語での説明があり、故障などのトラブルが発生した際の保証がしっかり受けられる点が魅力です。
2023年11月現在、楽天市場にも公式ショップ、大同電鍋楽天市場店がオープンしているので、楽天ポイントも活用できます。
ちなみに大手家電量販店では大同電鍋の取り扱いは、店頭・通販ともにありません。
以前、ヨドバシカメラでは2017年11月に2,000台が限定発売されましたが、2018年1月現在は新たに販売されていません。
Amazon.comにも公式ショップがオープンしているので、日本語表示の正規品を購入することができます。
ちなみに大同の無水調理ができるグリル鍋「Fusion Cooker(フュージョンクッカー)」は、各家電量販店で購入が可能です。
レシピごとにパーツを替えることで、IHクッキングヒーター、ホットプレート、土鍋・すき焼き鍋、鋳物ホーロー鍋、オーブン的に使えます。
Fusion Cooker(フュージョンクッカー)についてくわしくは下記の記事で紹介しているので、よろしければご一読ください。
台湾で購入するメリット・デメリット
台湾で日本の電化製品が使えるように、日本でも台湾の電化製品が使えるので「台湾で大同電鍋を購入する」のも一つの方法です。
台湾で大同電鍋を購入可能な店舗としては、家電量販店チェーンの「全國電子」や「燦坤」、デパートの家電売り場、大同3C(大同公司の直営店舗)、フランス系量販店の「Carrefour(カルフール)」などが挙げられます。
いずれも都市部や市街地にあるようなお店ばかりなので、見つけるのは難しくないと思います。
台湾現地で購入するメリットは以下の通りです。
・実際に自分の目で見て触って購入を検討できる。
・大同以外にも「日光(Nikko)」や「多偉(Dowai)」、「牛頭(BUFFALO)」など、他メーカーの電鍋も比較可能。
・日本では取り扱いのない大きさやカラーなど、バリエーションが豊富にある。
・上下レバー式の大同電鍋(旧型)が買える。
ただし炊飯器の比ではないくらい、外箱がかなり大きくて、中身も重いので、日本までの持ち帰りを考えると非常に苦労すると思います。
手持ちのスーツケースに大同電鍋が入るか、飛行機の手荷物や預け荷物にできるかどうかも考える必要があります。
台湾から日本へ荷物を送るには、郵便局やクロネコヤマト、佐川急便(台湾佐川)を利用する方法がありますが、ある程度慣れていないと難しいです。
大同電鍋の選び方
大同電鍋はYahoo!ショッピングなどの公式販売店で購入するのがもっとも確実な方法です。
ショッピングストアでは複数の取り扱いがあるので、各家庭にあった大同電鍋の選び方を紹介します。
サイズは「6人分」と「10人分」の2択
大同電鍋の大きさは、炊飯器のような「合」ではなく「人分(台湾表記:人份)」で表記されています。
日本で購入可能なのは「M(6人分)」と「L(10人分)」の2サイズですが、台湾では「3人分」や「15人分」「20人分」もあります。
日本人のほとんどは「6人分」を購入しますが、台湾の一般家庭では「10人分」が定番サイズです。
ちなみに私が持っている大同電鍋は「10人份」で、台湾からの友人のプレゼントで頂いたものなのですが、当時は一人暮らしだったこともあり「何でこのサイズを選んだの?!」と思ったのですが、台湾の方の感覚にしてみれば普通のようです。
| Mサイズ | Lサイズ | |
|---|---|---|
| 最大炊飯容量 | 1.08L(6合炊き) | 1.8L(10合炊き) |
| 高さ ✕ 幅 ✕ 奥行(cm) | 24.0 ✕ 31.0 ✕ 25.5 | 25.6 ✕ 34.8 ✕ 29.0 |
| 重さ | 3.2kg | 4.4kg |
付属品として、スチームプレート、内釜、フタ、アース線、計量カップ、しゃもじがセットになっています。
私の大同電鍋には、内釜とフタが大きさ違いで2つ入っていました。
カラーバリエーションは7種類
日本で販売されている大同電鍋のカラーバリエーションは緑、チャコールグレー、白、アクアブルー、赤、きはだ色、ネイビーブルーが用意されています。
鋳物ホーロー鍋のように、調理によって外側が汚れることはないので、キッチンの色合いや雰囲気、好みで選べます。
定番色は「赤」と「緑」の2色ですが、電化製品を白系で統一しているのであれば「白」も選択肢の候補として充分にありです。
「加熱」「保温」のスイッチの仕様

大同電鍋のスイッチの仕様は「旧型」と「新型」の2種類あり、日本で購入可能なのは「新型」一択です。
◆新型
レバースイッチを下ろすことで「炊飯(加熱)」になります。
「保温スイッチ」を押すことで、保温のオンオフが切り替えられます。
◆旧型
レバースイッチを下ろすと、炊飯(加熱)が開始されて、加熱が終了するとレバーが上がり保温状態になります。
コンセントを抜くと保温が切れます。
「昔ながらのレバーだけの大同電鍋が欲しい」という場合は、台湾まで買いに行く必要があります。
大同電鍋は購入すべき?
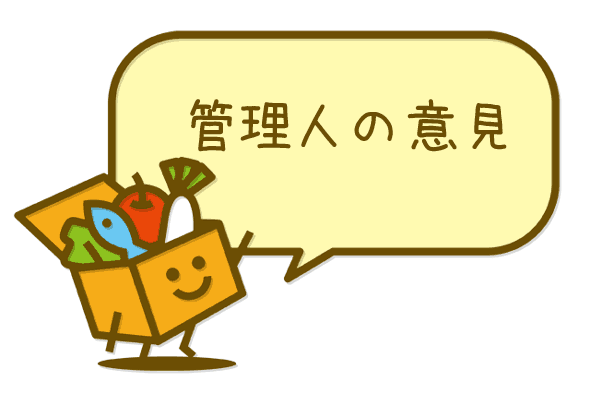
電鍋は「材料と水を入れて、スイッチを下げるだけ」の超シンプル構造の万能調理鍋です。
お米が6合(Mサイズ)や10合(Lサイズ)炊けるだけの大容量サイズなので、大鍋がない家でも重宝します。
「最近の調理家電はボタンや操作が多くて面倒」「炊飯器調理だと、作れる分量に限界がある」など、手持ちの調理器具に不満があれば、大同電鍋一つあれば使い勝手はよいと思います。
また基本的にスイッチを下げたあとは放置でOKなので「子どもの世話があるので、ずっと火の近くにいれない」という家庭でも使いやすいです。
ただし調理中は電鍋本体が非常に熱くなるので、子どもが触らないように注意が必要になります。
使い始めは「外釜の水は何杯入れればいいの?」「大同電鍋で何作ったらいいの?」といろいろと悩むと思います。
使っていくうちに「まぁ適当でいいか」「家に大鍋がないorコンロが空いてないから、大同電鍋で作るか」となっていくので、何度か使ってみて自分なりの使い方を見付けていけるのが、電鍋の魅力とも言えます。

 関連記事
関連記事










